数年前はそんな雰囲気はなかったと思いますが、やっぱり足元の高インフレ&円安が効いてるんでしょうかね。個人的にはあまり懸念していませんでしたが、極右ポピュリズム台頭で結構危機感を抱いています。
それでもハイパーインフレを見越して今のうちに与信を使ってマンションを買っておこうみたいなのとか、株式で持ってるからセーフみたいな人が多いように感じるのですが、実際に国家がその気になったら証券口座は一瞬で凍結されるでしょうし、不動産も自宅をいきなり接収とかはないとしても安全とは言い難い気がするんですよね。
たとえばGPT-5で出した過去のハイパーインフレ事例はこんな感じです。(未検証です。)
ブラジル(1990, コロル・プラン)月次インフレが70〜80%台まで加速した直後、民間の銀行預金や金融資産の約80%を最長18か月凍結。当時の政令・公式説明と報道がこれを確認しています。月次79〜84%(1990年3月)の記録も残っています。アルゼンチン(2001–02, コラリート/ペソ化)2001年12月に預金引き出し制限(コラリート)、続いて2002年にドル建て預金・貸付の“非対称ペソ化”という強制通貨転換(例:預金$1→1.4ペソ、貸付$1→1ペソ)と預金の強制リストラ(コラロン)。IMF・NBER等が経緯を詳述。ユーゴスラビア(1990–94)ハイパーインフレ期の前後に、家計の外貨建て預金を“凍結”。ECHR資料や研究レポートに記録があり、長期にわたり引き出せない状態が続きました。ジンバブエ(2000年代〜、2019年)2000年以降の大規模な農地収用(ファストトラック土地改革)は国際機関・人権団体の報告に残る“実物資産の収用”の典型。さらに2019年の法令SI 33/2019で、国内のUSD建て預金・残高を法定レート1:1でRTGSドルへ強制転換→その後RTGSが急減価、実質的な価値毀損が発生。ベネズエラ(2007–12以降)石油・電力・電信・セメント等の相次ぐ国有化・収用(補償の有無は事案により相違)。この国有化ラウンドはのちの高インフレ〜ハイパーインフレ期の前段から進行。ワイマール期ドイツ(1920s)ここは「没収」よりも、家主のインフレ“利得”を回収する目的の特別税(Hauszinssteuer, 1924)や、一時的資本課徴金(Reichsnotopfer)などの臨時課税で対応したタイプ。
日本で政府が取りうるオプションです。(これもとりあえず出しただけなので未検証です。)
政府・当局が取り得る主なオプション(法令・先例)1) 外為法による資本移動・支払の非常停止/制限非常停止(第9条):国際経済に急変→政令で一定期間、対外取引や支払等の停止を命令可能。支払通貨の指定(第8条)も併用でき、国内取引の円建て強制も制度上は可能。支払等の制限(第16条の2):許可制を課したうえで無許可の対外支払を個人単位で1年以内の範囲で禁止(銀行・資金移動業者経由の送金など)。外国為替令は緊急時の資本取引の制限対象を具体化。2) 1946年の先例:新円切替・預金封鎖・財産税(資本レバレッジの総リセット)金融緊急措置令・日本銀行券預入令(1946/2)で預貯金の封鎖、旧券→新券、払出し配給制を実施。日本銀行・国立公文書館が一次説明を公開。その後、一回限りの超累進の「財産税」(個人資産に25〜90%)で資産側にも大ナイフ。財務省・研究資料に税率や時系列がまとまっています。3) 銀行の破綻処理:預金保険+TLAC(大手行のベイルイン債)預金保険の原則:決済用預金は全額、それ以外は1金融機関あたり元本1,000万円+利息まで。システミック・リスク時には例外的に全額保護を発動し得る仕組みも明文化。大手G-SIBs(3メガ)はTLAC規制下。危機時は株主・劣後債・一部シニア債の順で損失吸収(ベイルイン)が前提。債券保有者は公的資金注入よりも先に負担します。4) 証券市場の臨時規制(流動性の蛇口を締める系)空売りの価格規制(トリガー方式)、売買停止(適時開示等)、サーキットブレーカー(先物・OP)、Dynamic Circuit Breaker等でパニック抑制。5) 生命保険の破綻処理(契約者負担が前提)1997–2001の一連の破綻では責任準備金の削減(原則90%保障)や予定利率の引下げが実施。契約条件は維持されず、契約者が相応の負担を負った先例。6) 不動産・資産への特別課税強化(先例あり)戦後の財産税は周知の通り。加えて地価高騰期には地価税(1991創設→1998停止)など「目的税」での土地保有課税の強化を実施した先例。まとめ:日本でも“口座・支払の統制/通貨指定/市場制限/破綻処理の損失負担/臨時課税”の武器庫は揃っている。平時は封印、有事は使える。
日本がハイパーインフレに陥ったときのアセットとして強いのは、海外法域で直接保有のTビル(購買力保全・資本規制耐性)、海外割当保管の現物ゴールド(購買力保全・接収耐性)、自己管理BTC(接収耐性・資本規制耐性)とのこと。
実際のところどうなのかはよく分かりませんが、富裕層なら海外割当保管の現物ゴールドは結構良いのかもしれませんね。現物ゴールドを自己管理していても島国(というか陸続きでも無理そう?)では国外には容易に持ち出せないので。
そういえばレイ・ダリオがBTCはプライバシーがなくて政府が追えるのでゴールドのほうが良いんだみたいなことを言ってた気がしますが、富裕層はこういう仕組みを使ってゴールドを分散保管しているので政府が把握しにくくなってるんですかね。現代は規制が厳しいので把握できなくするのは無理でしょうけど。
海外口座も税金逃れ的な意味では昔とは違って無意味になったみたいな話はよく耳にするものの、自国のハイパーインフレ対策という意味では結構強そうです。
今から海外口座に移動させるのは面倒ですし税制上もややこしそうなのでもう良いかなと思っていますが、BTCとかゴールドが好きじゃない人は口座を複数国に分散させるのは良いのかもしれません。
ハイパーインフレを想定するとFIREどころじゃなくなるので何とか耐えてほしいですね。
ハイパーインフレを想定するとFIREどころじゃなくなるので何とか耐えてほしいですね。
よろしければ応援クリックお願いします
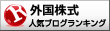 |
コメント