市場参加者は株式を基準として、そのヘッジ機能の度合い(株式との相関)によって債券利回りが決定されるというのは逆転の発想ですが、長期でみると時期によってかなり上下する債券とは違って株式(米国株だけでなく戦争等の影響を受けていない先進国株式)の実質リターンは安定的に6〜7%で推移してきたので、株式こそが基準という考え方も直感的には納得できる感じもします。
過去記事:長期上昇トレンドへの信仰心
ただ、債券の長期的な実質リターンが不安定になったのは最近のことで、米国の場合は昔は債券と株式のリターンはほとんど変わらなかったというデータもあったりします。
債券が明確にアンダーパフォームするようになったのはオーソドックスな金本位制が終わった1930年代くらいからのように見えるので、「金本位制下で貨幣供給に制約があった頃には名実ともに債券が完全なアンカーであったが、法定通貨になって制約がなくなったあとは債券が実質的にはアンカーとしての機能を失って株式と主従が逆転した」みたいに考えることもできるのかなと。
現代では(少なくとも日本の個人では)投資というと債券よりも断然株式ですし、債券を基準に考えている人は少なくなっているような気がします。
よろしければ応援クリックお願いします
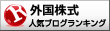 |
コメント